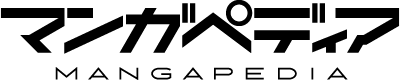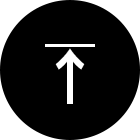あらすじ
第1巻
サラリーマン兼マンガ家の田中圭一は、2005年頃から原因不明のつらさ、恐怖や不安感など、謎の苦痛に苛まれ、悩まされていた。当時はどんな作品に触れても、どんなモノを見ても何の感情も湧かず、体も心もすべてが灰色になってしまったかのような感覚にもだえ苦しみながら、会社勤めとマンガ執筆で365日働きづめの日々を送っていた。そんな圭一を蝕んでいたものは、うつ病だった。彼は、かつて勤めていた会社の社長からウソをつかれたことにより転職。転職先で自分に合わない仕事を無理に続けた結果、周囲からの風当たりが強くなり、自己嫌悪に陥る。それが引き金となり、圭一は長いうつトンネルに入ってしまったのである。その後、病院に通い始めた圭一は精神安定剤を常用するようになるが、症状は改善されず、このまま薬の量が増え続けることに不安を感じ、主治医に相談なく勝手な自己判断で薬をやめてしまう。その反動なのか、とてつもなく大きな不安感に襲われた圭一は、医者に現状を包み隠さず相談するが、そこで主治医が発した言葉は、「あなたのうつ病は一生ものです」というものだった。これをきっかけに、主治医に不信感を募らせた圭一は、病院を転々として病状はさらに泥沼の様相を呈していく。そんなある日、圭一はコンビニエンスストアの文庫本売り場で、たまたま一冊の本に目を留める。その本には、うつ病になった精神科医が、自ら考えた方法でうつを脱した体験が記されていた。そして、この本との出会いをきっかけに、10年近く続いたうつトンネルから脱した圭一は、今もトンネルの中で苦しむかつての自分にような人々を救いたいと考えるようになる。(第1話「田中圭一の場合①」、第2話「田中圭一の場合②」、第3話「田中圭一の場合③」。ほか、18エピソード収録)
メディアミックス
登場人物・キャラクター
田中 圭一 (たなか けいいち) 主人公
漫画家を生業とする中年男性。1962年5月4日生まれ。うつ病に悩まされた経験があり、そのつらさを知っているため、今もうつトンネルを抜け出せず、苦しんでいる人たちの手助けをしたいと考えている。2000年... 関連ページ:田中 圭一
カネコ
田中圭一の漫画アシスタントを務める男性。大きな水玉模様のスーツを着用し、頭には宇宙人のような目が付いている。圭一の語る自らのうつ病体験談や、さまざまな人の体験談の聞き役を担っている。基本的にうつ病の人の気持ちはわからないため、話の途中で疑問に思ったことは率直にぶつけ、ストレートなツッコミを入れる。辛辣な言葉も少なくないが、そこに悪意はなく圭一には、カネコの言葉はうつ病を知らない一般人の感覚を代表するものととらえられている。AV作品に非常に詳しい。
照美 八角 (てるみ はっかく)
ゲームクリエイターの男性。1980年代後半のファミコン全盛期だった時代に、ソフトは作れば作るだけ大ヒットするという状況下、大手ゲームメーカーで照美八角自身もヒット作を連発した。その実績が社長の目に留まり、会社のビッグプロジェクトを27歳の若さで任されることになった。それは、ディズニーランドのアトラクション「スター・ツアーズ」にゲーム要素を取り入れたキャラクターゲームで、元々アメコミやアメリカのゲームが好きだった八角にとっては非常にやりがいのあるプロジェクトだった。しかし企画内容とは裏腹に、実現するための技術が追い付いていなかったため、問題は山積となる。上層部からの期待と重圧、一向に解決しない技術的な課題により、会社に週6日泊まり込んでも現場は遅々として進まない悪状況に陥った。そんな中、髪が伸びたからと会社のトイレで突然散髪を始めるという異常行動を起こす。心身共に限界が近かったにもかかわらず、それに気づかぬふりをして、何としてもやりとげなければならないという強迫観念にとらわれた結果、無理をしすぎて自分を壊し、体が動かなくなって長期にわたり会社を休むこととなった。そのうえ、自らのプロジェクトは他者にゆだねられ、安易なゲームとして世に出たことにショックを受けてしまう。その後は会社に復帰したものの、プライドはズタボロの状態となり、1995年に退社。この時点ですでにうつ状態に陥っており、死に場所を探すためにバイクであてのない旅に出た。気の向くままに行き先を決め、毎日いろいろな温泉に浸かって仕事とは無縁になった自分を傍観しているうちに、すべてがどうでもよく思えてきて、気が楽になる瞬間を迎える。そんな中、ライバルチームのディレクターを務めていた男性からの連絡を受け、これまでの八角の仕事ぶりを肯定し、これからの自分を必要としてくれる言葉を掛けられたことで、長らく抜け出せなかったうつトンネルの出口を見出すきっかけとなった。
折 晴子 (おり はるこ)
雑誌編集者を務める女性。8歳の頃に両親が離婚することになり、かわいくて愛想のいい弟と妹は、父親とその恋人に引き取られることになった。その際に父親から、おまえはどうすると尋ねられたが、折晴子は場の空気を察して母親のもとへ行くことを選んだ。その瞬間、父親が見せたあからさまにほっとした表情が原因で、私さえいなければこの場はうまくいくという、状況が行き詰まったら自分を引き算する考え方が身についてしまった。その後、成績は優秀だったものの、成長するにつれて母親とソリが合わなくなり、自意識が強く頑固な性格をかわいげがないと言われ続けた結果、傲慢なのに自己評価が低いまま育つことになった。漫画雑誌の編集者となったあと、30歳で編集長を任されることになるが、玩具メーカーとのタイアップ企画が持ち上がり、雑誌を買わないと手に入らないレアカードを付録にするという、当時としては無謀な企画をごり押しした結果、雑誌は販売部数が一気に3倍になる大ヒットを記録し、社長賞を受賞するに至った。そこで初めて自分に自信を持つことができたが、ビギナーズラックのような成功で変な自信をつけてしまったため、無理難題を部下に押し付け、パワハラで訴えられてもおかしくないような暴君へと変貌を遂げる。それでも業績は上がらず、晴子自身に実力がないことを周囲から責められ始めたのをきっかけに、体調の変化や耐えられない不安感に襲われるようになった。その後、雑誌の統合をきっかけに異動願を出し、自ら編集者としての人生をあきらめることを決断。それからは心療内科に通いつつ、宣伝部でのんびりと仕事をする日々を送っていた。しかしその後も、自分を引き算して、若い頃からの夢だった編集者をやめてしまったことへの後悔に苛まれた。そんなある日、文芸誌の創刊に宣伝担当として加わった際、編集長から編集者として必要とされることになり、念願だった文芸誌の編集者を務めることになり現在に至る。うつ症状とは完全に決別できていないが、趣味の登山の最中に自分の状態を知るきっかけを得て、最近では状態がずいぶん楽になってきている。
大槻 ケンヂ (おおつき けんぢ)
ロックミュージシャンの男性。そもそもミュージシャンになるつもりはなかったが、何者かになりたいという自己実現欲求だけは強く持っていたため、1980年代のバンドブームで、思いつくままに仲間とバンドを結成。適当な気持ちでバンド「筋肉少女帯」を組んだところ、22歳の時に大ブレイクし、24歳で日本武道館のステージに立つことになった。しかし、もともとネガティブな思考の持ち主だったこともあり、自分たちの人気が理解できず、こんなすごい状況が続くわけがないと不安と恐ろしさに襲われていた。そんな中、1995年に起きた天災やテロ活動により、パニック障害や不安神経症が発症。さらには、生きることへの執着や死への恐怖が極端に強い「ヒポコンドリー性基調者」の性格が仇となり、うつ病に加えて自分が不治の病であるという妄想に取りつかれる心気症までも患うこととなった。それでも孤独感を恐れていた大槻ケンヂにとって、芸能活動は世界とつながっていることを実感できる唯一の時間だったため、仕事は問題なく続けることができていた。ある時、うつ症状は自分の持つ心の闇に集中していることだということに気づき、そのエネルギーを別なものに向けてみようとプラモデルを延々と作ったり、極真空手をはじめとしたスポーツを始める。その流れで心療内科に通院して薬を飲みつつ、本を読み漁り始めたところ、仏教の考え方を取り入れた治療法「森田療法」と出会い、内面の変化を覚えるようになる。実在の人物、大槻ケンヂがモデル。
深海 昇 (ふかみ のぼる)
編集者を務める男性。入社早々、立て続けにゲーム攻略本やアニメ研究本などの企画を出し、ミリオンセラーの大ヒットを記録。仕事としては大成功を収めたにもかかわらず、これは人気ゲームや人気アニメがあっての成功であり、本を作ったのはライターやデザイナーであって、編集者の自分は何をしたのかと疑問を感じ、不安感を持ち始めた。そんな中、次も頼むという上司の言葉が第1の引き金となり、うつが発症。同時期に3年付き合っていた女性にプロポーズしたものの、相手は人妻で12歳の娘がいたことが発覚。精神的ショックを受けたことが、第2の引き金となりうつ症状が重くなっていく。日々つらそうにしている深海昇の姿を見かねた上司からの勧めで心療内科にかかり、重度のうつ病であると診断を受けたことをきっかけに休職し、彼女とも別れて自宅療養を開始。だがある日、突然自転車で深夜の公園を走り回ったり、友人の女性を口説いてみたりと、ふつうのうつとは違う症状が現れ始める。これによって自分がうつ病ではなく、ハイになったり落ち込んだりを繰り返す「双極性障害」であることをが発覚するが、双極性障害の投薬治療の効果は思わしくなく、次々と薬を変えても状況が改善されなかった。そんな中、医者を変えてみてはという上司からの勧めで別の病院を訪ねたところ、新しい医師は前の医師の処方や治療のすべてを高く評価し、前の医師がベストを尽くしていたことを告げられる。これにより心のモヤモヤが晴れ、改めて前の医師のもとへと戻り、病気と闘うことを決意。同時に双極性障害は劇的に治るものではなく、時間が一番の薬であるということを知り、医者から処方される薬や治療法を信じることの大切さを悟る。このことが、うつトンネルを抜け出す大きなきっかけとなった。
戸地湖 森奈 (とじこ もりな)
元高校教師の女性。最初に赴任した高校は、県内でも屈指の厳しい学校だったが、元々ルールを押し付けたり権威をふりかざすことが大嫌いだったため、学校の無意味に厳しいルールに対しては、闘う姿勢を見せていた。実はこの高校には生徒を留年させないという不文律があり、成績が悪い生徒に退学か転校をするように圧力をかけていた。それを知った戸地湖森奈は、たった一人で上層部とやり合うものの、何の成果も上げることはできず、異動願を出して別の学校に赴任するようになった。時を同じくして、趣味で始めた演劇サークルでは、自分の書いた脚本に何度もダメ出しされ、サークル内のつつかれ役になってしまう。このことが、気づかぬうちに森奈の精神を蝕み、いつしかうつトンネルに踏み入ってしまう。体が思うように動かないため仕事がはかどらず、好きな本やマンガ、映画やゲームのすべてが頭に入って来なくなる不気味な感覚に陥り、毎日ビールを飲んで前後不覚にならないと寝付けなくなってしまう。そして、とうとう駅のホームでひたすら線路を見つめるようになり、友人からの指摘を受けて精神科を受診し、うつ病の診断を受ける。その後、投薬を続けながら教壇に立ったものの、不調に耐えられず1年半休職。その後も復職と再発、休職を繰り返すことになる。実は小学生の頃、とあるトラブルをきっかけに誰からも理解されない苦しみを知り、以降は他人と一定の距離を取って付き合うようになった経緯がある。担当医師とのカウンセリング中にそのことを思い出し、本当は自分を理解してくれる友達が欲しかったのだと気づいた時、15年もの長きにわたって、苦しみ続けてきたうつトンネルの出口を見ることになる。
岩波 力也 (いわなみ りきや)
メーカーで総務を務める男性。以前、うつ病を患って5年ほどうつトンネルをさまよっていたが、その間も会社を休むことなく、しんどい体にムチ打って勤務を続けていた。岩波力也自身の担当部署はほとんど一人で回していたため、気力と責任感だけでギリギリのところで仕事を続けていたが、ある時上司からフラフラしながら仕事をするくらいなら、いっそのこと休んでくれた方が気が楽だと言われる。当時はその言葉に腹を立て、落ち込んでいたが、その後うつトンネルを抜けて正常な思考に戻ってから考えると、上司はギリギリで働いていた自分を見て、心配を通り越して死んだりしないだろうかと、気を揉んでいたと推察。上司が感じた不安と恐怖に思い至らなかったこと、上司の忠告通り休養を取っていたら、こうはならなかったのではないかと自らの行いを反省する。
姉原 涼子 (あねはら りょうこ)
アパレルメーカーで営業部長を務める女性。かつて、部下の半田聖子の存在がストレスの原因となり、うつ病を患っていた。聖子は事あるごとに自分につっかかってきたため、涼子のうつが日に日に悪化していった。その後、聖子は異動となり、聖子の友人の女性が新たに配属されてきたが、彼女から聖子が姉原涼子自身に強くあこがれを抱いていたことを聞かされる。そして聖子が、父子家庭で育ったことで甘え下手になり、つっかかることでしか相手の愛情を図れなくなったという事情を知る。その後、無事うつトンネルを抜けて現在に至るが、当時は心が弱っていたため、聖子の変化球のような愛情表現に気づいてあげられなかったと当時の自分を振り返り、視点を変えてみることの大切さを悟る。
半田 聖子 (はんだ せいこ)
アパレルメーカーの営業部に勤める女性。姉原涼子の部下で、気が非常に強い。父子家庭で育ち、母親や姉のような甘えられる女性を欲しているが、甘え方を知らないため、つい相手につっかかってしまう。かまって欲しい相手には、強く嚙みつき、相手の愛情度を試してしまうところがある。涼子に対して強いあこがれの気持ちを持っているが、素直に甘えることができず、事あるごとにつっかかり続けた結果、うつ病だった涼子にさらなるストレスを与えることになってしまう。その後、部署を移動することになるが、現在でも何かと理由とつけては涼子とかかわりを持ちたがり、営業部に顔を出している。
代々木 忠 (よよぎ ただし)
AV監督を務める男性。愛のあるセックスをテーマにAV作品を撮ることで有名。AV撮影の現場で多重人格の女性と知り合ったことがきっかけで、さまざまな多重人格者との交流を始め、彼女たちを救おうとした。しかし2003年頃から、夕方になると背中と胸の中心が痛くなるという症状に見舞われるようになった。息苦しさや不安感、孤独感、悲しみに苛まれ、気力がすべて失われるような状況が何年も続き、うつ病であることが判明する。3歳の時に母親と死別し、少年時代はケンカに明け暮れ、極道になってからは義兄弟との確執から命を狙われていた。その後、ポルノ映画の監督になるが、代々木忠自身がプロデュースした作品がわいせつだと判断され、長期間に及ぶ裁判の中で、学歴や前科で差別されつつも闘ってきた経緯がある。さらには、生まれて4日で娘を亡くすなど、苦しさを感じる余裕もないほど波乱に満ちた人生を送っていたが、当時は体に特段の変調はなかった。しかし、うつを患ってからは強烈な吐き気や下痢、全身の激痛などにも悩まされ始める。解放されたい、楽になりたいと思い悩む毎日を送っていたが、ある友人から聞いた話をきっかけに、十字真言を唱えることでうつトンネルを抜ける一つのきっかけを得る。催眠の世界を心得ていることもあり、この痛みや苦しみを生み出すものはすべて自分の心の中にあるということに気づくことになる。また霊感の強いAV女優から、「子供の頃の監督が寂しいと言っている」と言われたことが二つ目のきっかけになり、うつから脱する答えを見出すことになった。実在の人物、代々木忠がモデル。
宮内 悠介 (みやうち ゆうすけ)
小説家の男性。もともとはプログラマーで、2000年に友人と共に音楽ソフトの会社を立ち上げた。当時は忙しくも充実した日々を送っており、深夜に帰宅して新人賞向けの小説を執筆する毎日が面白く、根拠のない自信とやる気に満ちていた。そんな中、さらにやる気が高じて仕事仲間のために職場環境をよくしようと、管理職を兼任することを志願した。しかし、性格的に不向きなことをわかっていながら、それにふたをして無理矢理頑張ったため、うつ病発症のトリガーを引いてしまうことになる。その後、リーマンショックの余波もあり、一つの取引先に頼らざるを得ない状況となり、山のように降って来る仕事をあくせくとこなすはめになる。その結果、当初の思惑とは真逆に仲間に無理な激務を強いることとなった。それが原因で精神的重圧を受け、字が読めない、文字が追えないなどの症状に見舞われるようになり、最終的には体がまったく動かない事態に陥り、10年以上まともに会話すらしていなかった母親に助けを求めた。その直後、会社を辞めて実家に戻ることを決断。すべてのプライドを捨て、自分の心の病と向き合うことにした。心療内科に通い始めたことで少しずつ回復していく中、以前執筆した小説『盤上の夜』が第一回創元SF短編賞の選考委員特別賞を受賞し、小説家としてデビュー。これによって自信を取り戻し、うつトンネルから抜け出すことにつながった。現在はうつ症状は寛解しているものの、時々突然やって来るリターンがあり、完全にうつ状態を抜けきることはできていないが、自らの中にあるうつスイッチとは、うまく付き合っている。実在の人物、宮内悠介がモデル。
鴨川 良太 (かもがわ りょうた)
ライターを務める男性。若い頃からメンタルが弱く、被害妄想が強い傾向にあった。25歳の頃、勤めていた編集部で、「きみの仕事はもうここにはない」と上司から言われる。見捨てられたと感じて布団から起き上がれなくなり、そのまま出社しなくなった。さらに5年後、別の会社で根も葉もない噂を流され、仕事がなくなる事態に陥り、またもや自分は不要な人間なんだと思い詰め、トイレから出られなくなってしまう。その後、かかわった出版社で内紛が起こり、会社が分裂する騒ぎになった。その際、鴨川良太自身の力が必要とされることになり、その責務を果たすことで無自覚なうつトンネルから脱することになる。そのあとに起こった3月11日の東日本大震災と原発事故に対して、ネット上でデマが横行した際、自分の心の中にふくれあがる不安を抑え込むかのように火消しに奔走した。この生活を2週間続けた結果、心に溜まった不安がピークに達し、今までネット上では安全だと発信し続けてきたにもかかわらず、妻に「関西に逃げよう」と口走ってしまう。これを聞いた妻からは「バカ」と一喝され、締め切った窓を開け、部屋の掃除を始めるようにと指示される。二人がかりで始めた大掃除が終わってみると、気分が晴れやかになり、久しぶりに町へ出ると節電で薄暗く、ノスタルジックな雰囲気に愕然とする。みんなが共に立ち上がろうとしていることを感じ、自分も頑張ろうと思うきっかけとなった。
ゆうき ゆう
精神科医を務める男性。ソウの『マンガで分かる心療内科』の原作者でもある。医師としての立場から、うつ病患者を分析している。悪いように思い込んでしまう思考のクセを見つけ出し、認知の歪みに気づいて貰うことを目的として、カウンセリングを行っている。また、ものごとを客観視するために、客観的事実と主観的感想を1:1の比率で日記に記すことを勧めている。そうすることで、時間を置いて読み返した時に自分の悩みがさほど大きくなかったと実感できるとしている。また、うつ病の再発に関しては、気分的に落ち込んだ時は人生の自習時間と考え、自習時間にふさわしい「やるべきこと」を見つけておくのが大切だと教えている。ネガティブ思考に陥りやすい人は、危険を回避しやすく生き残る可能性が高いのだから、ネガティブな自分は優秀というくらいに自分を肯定すべきと考えている。実在の人物、ゆうきゆうがモデル。
ずんずん
「プロの外資系OL」を自称する社畜体質の女性。求められると過剰に頑張ってしまう気質を持ち、権威に弱く、NOと言えない性格をしている。大学を出て入社した超一流メーカーは、超一流ブラック企業だった。朝は7時から夜は終電まで仕事で、休日出勤も当たり前の毎日を送っていた。ものすごい勢いで人が辞めていくので、会社にとって人間なんて使い捨ての部品のようなものだと体感する中、入社半年で責任者を任されることになった。山のように降って来る仕事により、睡眠不足でミスが増える日々に、すべて自分がいけないといううつ症状の典型となる考え方が出始める。同時に文字が頭に入って来なくなり、心療内科を受診。医者からの指示で、一か月会社を休んだことでほどなく寛解した。それを機に別の外資系企業に再就職するが、そこも徹夜して頑張るのが偉いという風潮がある会社だった。そんな中、3月11日の東日本大震災が発生して、ほかの会社の人が次々と帰宅する中で、仕事を続けることを強制されたことにより、再びうつ症状に悩まされることになった。その後、シンガポールで受けていた「コーチング」というメソッドにより、ずんずんの社畜体質を作った原因が、彼女の生い立ちにあることが判明。中でも、亭主関白だった父親への恐怖や、父親から愛されたという自信がないことに起因することがわかった。これを機に父親に自分を大切に思うのかと改めて確認したことで、自分を長いあいだ縛り続けていたものが氷解し、うつトンネルを抜け出すことができた。
まつい なつき
エッセイスト兼占い師の女性。結婚して子供を産むのが当たり前という考えを持っており、31歳の時に婚約者から子供はいらないと言われたことがきっかけで、うつ病を発症。子供を見かけるだけで涙が出たり、嘔吐や胃けいれんで動けなくなったりと、パニック障害を併発。心療内科を受診し、担当医師から自分の責任だと思っていることを減らすようにとアドバイスを受け、心の重しになっていたものをすべて外し、婚約も解消した。仕事で各地を飛び回っていた当時、取材に同行していた男性カメラマンから、子供が欲しければオレの子を産めばいいと言われ、授かり婚をした。妊娠出産の喜びと子供を抱く感触に感動し、そのいきさつを綴った著書『笑う出産』を刊行すると、60万部の大ヒットを記録。それをきっかけに、次々とエッセイ本の仕事が舞い込むようになった。しかし、そんな自分とは対照的に夫の仕事は低迷。最終的にはゼロになり、部屋に閉じこもるようになってしまう。夫を心配するあまり、掛けた言葉が逆に夫を追い詰める結果となり、ほどなくして離婚した。仕事や家事、育児もすべて自分だけでやってみせると頑張ってみたものの、一番幸せにしなければならない人を幸せにできなかったという負い目から、うつ症状が再び発現。ゴミだまりとなった家の中で寝たきりとなり、エッセイを書くどころか、子供の面倒を見ることさえままならなくなってしまう。そんな中、三人の子供たちや近所の人のさりげないフォローや気遣いに助けられ、徐々によい方向へと向かっていった。しかしある日、部屋がすごい勢いで回転する幻覚に襲われ、自死が頭をよぎった時、子供たちの存在がまついなつきに光を見せ、思い出の詰まった家を引っ越して再出発することを決意。それがきっかけで、長いうつトンネルの先が見えるようになった。実在の人物、まついなつきがモデル。
牛島 えっさい (うしじま えっさい)
コミックマーケット準備会で部署責任者を務めていた男性。上層部からの指示を受け、現場で動くボランティアをまとめ上げる中間管理職のようなポジションにある。世界最大規模の同人誌即売会で、同人誌やコスプレイヤー、企業の限定グッズが勢ぞろいするオタクにとっての至上の祭典「コミックマーケット」の発展の立役者である米澤喜博は、牛島えっさいにとって恩師にあたる。しかし、幾度となく窮地に立たされたえっさいの支えとなった喜博が急逝したことで、大きな心の支えを失い、その喪失感から日常生活もままならなくなる。うつ病により、不安感や恐怖感、幻聴まで聞こえるようになったため、コミケ準備会を去ることを決断。しかしそれにより、大好きだったオタク趣味まで失うこととなり、失意のどん底に落ちた結果、無意識に自殺を図る。幸い未遂に終わり、その後の通院とカウンセリングで徐々に回復の兆しを見せる。病状がよくなり、気分が持ち直したのを機にコスプレイベントの会社を設立するが、うまくいかずに借金まみれになってしまう。このことを妻に打ち明け、形式的に離婚することを選択。その後は借金返済のため、建設業や警備の仕事に就くが、気分が落ち込み長続きしない状況が続いた。そんな中、趣味を理解し認めてくれた妻の存在、そして自分と同じ趣味を共有できる息子の存在が支えとなり、うつトンネルから抜けるきっかけとなった。のちに、うつ病ではなく双極性障害であることが判明した。
熊谷 達也 (くまがい たつや)
小説家の男性。両親の不仲により、子供の頃から心にストレスを溜め込みながらも順調に進学し、大学を出て埼玉の中学校で教職に就いた。仕事は大好きで、ほかの教師の倍は働くまじめな頑張り屋だったが、不良の生徒が多く、その対応に奔走することも少なくなかった。そのため、通勤途中の車の中で、学校に行きたくない気持ちを打ち消そうとし、大声を出しながらハンドルを叩くなど、気持ちを抑え込もうとしていた。その後、宮城県気仙沼市の中学校に赴任して、陸上部の顧問を務めたり、登山旅行をしたりして、生徒との交流が増えた。埼玉時代とは一転、多くの生徒に慕われ、楽しい日々を送っていたが、仕事量はさらに倍増していく。そんな中、そこで知り合った女性との結婚を機に、のどかな田舎の中学校へと異動。その翌年、冬休み明けの朝に突然うつ症状が発現。突然ふとんから起き上がれなくなり、一か月学校を休むことになった。その時妻から、つらいなら教師をやめてはどうかと前向きな提案をされたことで、ほかに選択肢があったことに気づくことができ、うつトンネルへの突入を回避することができた。その後、ほかの仕事に就きつつ合間に執筆した小説『ウエンカムイの爪』で作家デビューを果たし、2004年に『邂逅の森』で直木賞を受賞することになった。だが、2011年の東日本大震災を経験し、ふたたびうつ症状が出始める。被災地を舞台にした作品の執筆を始め、10年間で全20作のシリーズにしようと意気込んでいたが、5年で8冊執筆したところで、自分が一体何のために書いているのかという思いに囚われるようになる。だが、そのモデルとして選んだ被災地の気仙沼に足しげく通い、かつての教え子や友人と接する中で、自分が必要とされていることを実感することとなり、うつトンネルを脱することになった。実在の人物、熊谷達也がモデル。
内田 樹 (うちだ たつる)
フランス哲学研究者の男性。1992年に32歳で離婚を経験。まだ幼かった娘を連れ、女子大学の専任教員として東京から神戸に引っ越した。初めての女子大教員に娘との二人暮らし、慣れない家事など、そのストレスは非常に大きなものだったが、周囲の手助けもあり、徐々にうまく回り始めた時に不眠と激しい無力感に襲われるようになった。知人の勧めで心療内科を受診すると、担当医師から疲れすぎだと指摘された。気力も体力もあり、充実していると思い込んでいたが、元々責任感が強い性格のため、気を張ってストレスをはねのけていたつもりが、体はとうに限界を超えていたのだ。義理堅い性格ゆえ、それまでは這ってでも行かなければと考えていた冠婚葬祭に出席しないようにとの医師からの指示を受け、呪縛を解かれたような晴れやかな気持ちになり、ほどなく寛解。その後、1995年に阪神淡路大震災を経験。職場である大学が大きな被害を受けたため、大学の復旧に尽力した。しばらくして、半壊した自宅マンションが住めるようになり、半年ぶりに帰宅して片づけを始めた時、急激にうつ症状が悪化。震災時の大音響がフラッシュバックして、ちょっとした物音にも大きな恐怖を感じるようになり、不眠に悩むようになる。その後、睡眠導入剤の服用による副作用で記憶の混濁が起こり、仕事にも弊害が出たことで、さらに激しい自己否定の感情に襲われるようになった。だが、そんなうつトンネル真っ只中でも、合気道をしている時だけは自分を肯定することができた。合気道特有の考え方が、脳を休ませて体の声を聞くことにより、心の健康を取り戻すことにつながり、2年でうつトンネルから脱することができた。実在の人物、内田樹がモデル。
一色 伸幸 (いっしき のぶゆき)
脚本家の男性。1994年に何の前触れもなく、ある日突然風景から色が消えた。妻に付き添われて精神科を受診し、うつ病との診断を受けた。仕事や家庭、経済面もなんの不自由もなく、うつ病になる要因など何もなかったように思えたため、服薬で状態は改善するだろうと考えていたが、現実は甘くはなく、日に日に症状は悪化。うつトンネルの出口を探し続ける中、昔旅行で訪れて楽しかったパリに行こうと思い立った。しかし、結局パリには1週間滞在したものの、一度も外に出ることができないままベッドで過ごすことになる。その後帰国してからは、うつを治そうとすら思わなくなり、さらに状態は悪化し、ただ消えてなくなりたいと考えるようになった。元々自由業だったため、仕事をすることをやめ、ただ時間が過ぎるまま身を委ねていたのが功を奏し、2年間という時間をかけて少しずつ風景に色を取り戻し、気力も感情も取り戻すことができた。2007年には、現在うつ病に苦しむ家族のために、うつの正体を知って欲しいという思いから、自らのうつ病体験を記した手記『うつから帰って参りました』を刊行した。実在の人物、一色伸幸がモデル。