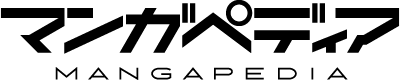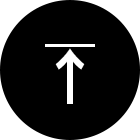あらすじ
苦楽の誕生
1923年(大正12年)9月1日、関東大震災により、東京は壊滅的な被害を受けてしまう。震災によって家と仕事を失った青年・川口松太郎は、恩師である小山内薫の招きに応じて下阪する。そして、プラトン社へと就職し、不良編集者の植村宗一(のちの直木三十五)と共に、新雑誌の創刊を目指して職務に励むのだった。一癖も二癖もある編集者や作家とのやり取りを経て、残るは植村が手掛けるゴシップ記事の脱稿を待つのみとなっていたが、植村は記事の執筆を放り出し、小説を書き始めてしまう。松太郎は困惑するが、できあがった『鑓の権三重帷子』は目の肥えた松太郎を唸らせるほどの傑作だった。振り回されてばかりだった松太郎は植村の文才に惚れ込むことになり、ぎこちなかった二人の関係にも変化が訪れようとしていた。そして同年12月、新雑誌は小山内に「苦楽」と名づけられ、世に送り出される。
ミューズの喪失
1924年(大正13年)2月、川口松太郎は挿絵画家の岩田専太郎をプラトン社に招く。しかし、専太郎の絵は植村宗一に古いと一蹴されてしまい、専太郎は画風を改めようと足掻(あが)き始める。やがて専太郎はプラトン社の美術担当・山名文夫から聞いた「芸術の湧き出る泉にはミューズがいる」という話を思い出し、大阪で再会した妹の岩田とし子こそ、自分に取ってのミューズであったことを思い知るのだった。同年6月13日、小山内薫が東京に築地小劇場を立ち上げる。松太郎と岩田兄妹は久しぶりの東京で観劇に興じ、その足で思い出の地を訪れるが、かつて三人で暮らした家は跡形もなかった。すべてを失ったことを痛感したとし子は「これしかない」と語り、東京に残って女優を目指すという決意を語るとともに、専太郎に別れを告げる。これに絶望した専太郎は官憲といざこざを起こし、癲狂院(てんきょういん)への強制入院を命じられてしまうが、狂いながらも舞の稽古を続けているという元芸者の姿に美しさを見いだし、挿絵画家として復活を遂げるのだった。
モダニズムの閃光
岩田専太郎が入院しているあいだにも次なる「苦楽」の編集作業は進行しており、小田富弥や国枝史郎などの才人が続々と参画していた。それはまったく新しい大衆文芸誌の完成を予感させたが、小山内薫が演劇に、植村宗一が映画に傾倒している状況を鑑みて、川口松太郎はプラトン社の終わりを意識せずにはいられなかった。翌年の春、松太郎は編集長となったが、そこに喜びはなかった。そして数年後、プラトン社に解散の時が訪れる。
登場人物・キャラクター
川口 松太郎 (かわぐち まつたろう)
関東大震災によって家と仕事を失った文士崩れの青年。年齢は1923年(大正12年)9月の時点で23歳。柔和な顔立ちで、眼鏡をかけている。真っすぐな性格だが、財布の紛失に気づかず鰻丼を注文して官憲につき出されそうになるなど、間の抜けた一面がある。実の両親の顔を知らず、中学校すら出ていない。学がないと謙遜しているが、文才には恵まれており、小山内薫の戯曲研究会に所属していた頃、インテリぞろいの会員を差し置いて帝国劇場から懸賞戯曲を高く評価されたことがあり、現在は小説家にあこがれている。震災後、小山内の招きに応じて下阪し、プラトン社の雑誌「苦楽」の創刊に携わることになった。当初は同僚の植村宗一を嫌っていたが、のちに彼の文才に惚れ込み、評価を改めている。また「小説と挿絵は飯と汁」という持論があり、親友の岩田専太郎を挿絵画家として起用した。なお、下阪するまではスタンドカラーのシャツに上衣と袴を合わせた和洋折衷の書生スタイルだったが、大阪で働き始めてからはハイカラなスーツを着るようになった。しかし、谷崎潤一郎から「書生っぽ」と揶揄されるなど、雰囲気は学生時代から変わっていない。実在の人物、川口松太郎がモデル。
植村 宗一 (うえむら しゅういち)
プラトン社で新雑誌の立ち上げを任された男性。年齢は1923年(大正12年)9月の時点で32歳。面長で鼻根の右側に黒子があり、着流し姿で下駄をはいている。肺が悪く薬を飲んでいるが、愛煙家でたばこを持ち歩いている。また、芸者遊びを嗜(たしな)む通人ながら、下戸である。初対面の相手にたばこを要求するなど、図々しい性格をしている。つねに金欠で、川口松太郎の財布を盗んだ疑惑もあるが、拾ったと主張し、すぐに返却している。原稿料の前借り常習犯でもあり、方々から煙たがられているが、編集者としては敏腕であり、「文藝春秋」で「文壇諸家価値調査表」を発表し、売上を数倍にしたことがある。芥川龍之介などの著名な作家と面識があり、彼らに原稿を書かせるという証文を携えてプラトン社に雇われることになったが、のちに証文はでっち上げだと白状している。しかし、結果として錚々(そうそう)たる面子の作品を集めることに成功し、面目躍如と相成った。並行してゴシップ記事の取材も進めていたが翻意して、『鑓の権三重帷子』で小説家デビューを飾り、松太郎から才能を絶賛され、仲を深めることになった。なお、ペンネームを何度も変更し、最終的に「直木三十五」を名乗ることとなる。実在の人物、直木三十五がモデル。
小山内 薫 (おさない かおる)
プラトン社で働く劇作家、演出家の男性。年齢は1923年(大正12年)9月の時点で42歳。口髭を蓄えており、背広を着て、蝶ネクタイを締めていることが多い。欧州遊学の経験があり、演劇は魂の芸術との持論を持つ。かつて自宅で開催していた戯曲研究会で川口松太郎の才を見いだし、目をかけるようになった。関東大震災の直後には焼失を免れた『プラトーン全集』を松太郎に譲渡し、彼をプラトン社へ誘っている。松太郎と植村宗一に新雑誌の編集を託したうえで、小山内薫自身も原稿をチェックしたり、家を失った松太郎を屋敷に住まわせたり、勉強のために文楽座に連れ出したりと世話を焼いていた。また、新雑誌が校了を迎える直前に誌名を「ライフ」から「苦楽」へと改めている。大正13年には東京に築地小劇場を設立した。しかし、「二年間は翻訳劇だけを公演する」という方針を打ち出したことで菊池寛を中心とする雑誌「演劇新潮」の面々と衝突し、批判を浴びる事態となってしまった。なお、松竹キネマ研究所第一回作品『路上の霊魂』の総指揮者として活動していた頃に狭心症の発作を起こして倒れたことがある。以来、忍び寄る死の気配に苛まれ、新興宗教に傾倒するようになってしまった。実在の人物、小山内薫がモデル。
岩田 専太郎 (いわた せんたろう)
「講談雑誌」で活躍していた挿絵画家の青年。年齢は1924年(大正13年)2月の時点で22歳。シャツに着物を合わせた和洋折衷の装いをしていることが多い。川口松太郎と親しく、妹の岩田とし子と共に同居していたこともある。松太郎の誘いで下阪し、雑誌「苦楽」で挿絵を担当することになった。鏑木清方風の美人画を得意としていたが、新しいものしか評価しないという植村宗一の発言を受け、絵柄を変えようと奮起する。山名文夫から創作の源泉たるミューズの話を聞かされ、遊女をモデルに絵を描くなど迷走していたが、やがて妹をモデルに絵を描いた時のことを思い出し、彼女こそ自分のミューズだと悟る。しかし、再会したばかりの妹から一方的に別れを告げられ、再びミューズとの別離を味わうことになってしまった。その後、自暴自棄に陥って官憲と諍(いさか)いを起こし、癲狂院(てんきょういん)への強制入院を余儀なくされた。癲狂院では3か月にわたって悪夢にうなされる日々を過ごし、一時的に絵を描くことができなくなってしまったが、頭がおかしくなっても舞の稽古を続けていた元芸者の姿に感動を覚え、退院後は挿絵の仕事に復帰している。実在の人物、岩田専太郎がモデル。
岩田 とし子 (いわた としこ)
岩田専太郎の妹。年齢は1924年(大正13年)2月の時点で20歳。断髪の髪型で、たばこを嗜(たしな)むモダンガールであり、その可憐な容姿からアサヒカフェの看板女給として親しまれている。「湊明子」という名前でブロマイドが販売されているほど人気があり、山名文夫から撮影を頼まれ、旗袍(チーパオ)姿を披露したこともある。美しいものを眺めていると涙が出るという繊細な心の持ち主だが、当人も自覚しているほどの跳ね返りで、感情に任せて平手打ちを放つことも少なくない。14歳の頃に、初めて兄である専太郎の絵のモデルになった際には取っ組み合いの喧嘩に発展し、兄の頭を皿で殴りつけている。ただし、この時は頰を殴り返され、鼻血を出すことになってしまう。浅草の清島町で川口松太郎や専太郎と同居していた時期もあり、飯炊きや絵のモデルをして彼らを支えていた。この同居生活は岩田とし子が前田重信(のちのサンケイ新聞出版局社長)に見初められて終わりを迎えたが、現在の彼女は「出戻り娘」である。のちに専太郎と大阪で偶然の再会を果たすことになったが、築地小劇場で見た『海戦』に感動して東京で女優を目指すことを決意し、専太郎に一方的な別れを告げている。実在の人物、湊明子がモデル。
菊池 寛 (きくち かん)
文芸王と囃(はや)される作家の男性。年齢は1923年(大正12年)の秋の時点で36歳。同人雑誌「新思潮」で頭角を現した。肥満体で口髭を蓄え、無精髭を生やし、着物姿で眼鏡をかけている。関東大震災の被害を受けて田端にある作家・室生犀星の家を借りて住んでいるが、自らの家族のみならず、妾の文栄とその家族、さらには女中までいっしょに暮らしているため、非常に手狭になっている。発売を控えていた「文芸藝秋」が焼失したことに絶望していたが、大正12年の秋に再出版のめどが立ち、祝賀会を実施した。この宴席には菊池寛に仕事を依頼するべく訪れていた植村宗一、同人の久米正雄も出席している。同日、植村の依頼に応じて戯曲『父帰る』を提供しているほか、妻の包子(かねこ)が産気づき、嫡子を得ている。翌年には築地小劇場のパーティーに出席している。この際、雑誌「演劇新潮」の作家たちに小山内薫を攻撃させ、川口松太郎から「人が悪い」と評されてしまう。実在の人物、菊池寛がモデル。
久米 正雄 (くめ まさお)
菊池寛、芥川龍之介と同じく同人雑誌「新思潮」で頭角を現した作家の男性。年齢は1923年(大正12年)の秋の時点で31歳。口髭を蓄えており、洋服姿で眼鏡をかけている。10代の頃から俊英として名を馳せ、俳人としても活動していた。今は亡き夏目漱石の門下生であり、漱石の娘である筆子に懸想していたが、同じく漱石の門下生である松岡譲に筆子を奪われ、茶屋で出会った芸者の女性と結婚することになった。大正12年の秋には「文芸藝秋」の再出版祝賀会に出席した。この際、泥酔して植村宗一の服装を祝いの席にふさわしくないと揶揄し、小説を書いて金を稼ぐように煽り立てた。これに対して、植村は久米正雄のヒット作『破船』が筆子との内実を晒したものである点を指摘したうえで、恋に破れて芸者を嫁にした男を題材に記事を書くと挑発的な返事をしている。しかし、結果として植村は時代小説の執筆に注力することになり、川口松太郎が久米の結婚を題材にしたゴシップ記事を引き継ぐことになった。翌年には築地小劇場のパーティーに出席している。この際、新聞に掲載された小山内薫の「本邦の作品には演出欲が唆(そそ)られない」という旨の発言を引き、論争の口火を切った。実在の人物、久米正雄がモデル。
芥川 龍之介 (あくたがわ りゅうのすけ)
菊池寛、久米正雄と同様に同人雑誌「新思潮」で頭角を現した作家の男性。年齢は1923年(大正12年)の秋の時点で31歳。端正な顔立ちで、スタンドカラーのシャツに着物を合わせて、下駄をはいている。関東大震災を「面白かった」と振り返るなど、浮世離れしたところがある。久米と同じく帝国大学の出身で、夏目漱石の門下生でもあるが、つねに久米よりも高い評価を受けており、文壇の麒麟児と囃(はや)されている。植村宗一が編集した「文壇諸家価値調査表」では学殖の項目で小山内薫の92点を凌ぐ96点という極めて高い評価を得ているが、腕力の項目では0点という最低の評価をされている。大正12年の秋には田端で植村と遭遇し、しばし雑談に興じている。この際、植村から千鳥足を指摘され、神経衰弱に陥って薬漬けになっていることを告白した。また、戯曲『ハムレット』を引用して植村の心に波紋を生じさせ、小説の執筆を決心させているが、それから4年も経たないうちに命を燃やし尽くしてしまう。なお、川口松太郎のあこがれの小説家であり、芥川に気に入られる妄想寸劇を松太郎が一人二役で演じて悦に浸る場面がある。実在の人物、芥川龍之介がモデル。
谷崎 潤一郎 (たにざき じゅんいちろう)
耽美派の巨人と囃(はや)される小説家の男性。年齢は関東大震災から数日後の時点で38歳。貫禄のある体つきで、和服と洋服を使い分けている。また、食べることが大好きで、つねに食べ物か飲み物を口にしている。小山内薫を尊敬しており、この世で先生と呼ぶにふさわしい唯一の人物と語っている。関東から大阪へと向かう船上で偶然にも小山内と再会することになり、被災した横浜の惨状を説明した。この際、小山内に今後を問われて、「生きることは書くこと」という持論について語るとともに、横浜が駄目になったら京都で、京都が駄目になったら神戸で、神戸も駄目になったら支那で書くと決意表明した。のちに川口松太郎と中華飯店で面会し、かつて小山内が放った「自由劇場を興したのは生きたいから」という旨の発言に感銘を受けたことを明かしている。この発言は松太郎にも影響を与えており、やがて松太郎を経由して苦境の最中にあった小山内へと立ち返ることになった。雑誌「苦楽」の創刊号には付録として戯曲を提供している。久保田万太郎と共に築地小劇場のパーティーにも出席しているが、派閥抗争よりも食事に夢中だった。岡本かの子が苦手。実在の人物、谷崎潤一郎がモデル。
久保田 万太郎 (くぼた まんたろう)
俳人、劇作家の男性。年齢は1924年(大正13年)6月の時点で35歳。和服姿で、眼鏡をかけている。かつて小山内薫が開催していた戯曲研究会に川口松太郎を紹介したことがあり、その後も講談師・悟道軒圓玉と共に松太郎に助言をするなどして、師匠と慕われるようになった。谷崎潤一郎と共に築地小劇場で行われたパーティーに出席することになり、この際に松太郎と再会している。実在の人物、久保田万太郎がモデル。
岸田 國士 (きしだ くにお)
戯曲、評論、翻訳、演出など手広く手がける作家の男性。年齢は1924年(大正13年)6月の時点で34歳。オールバックの髪型で、無精髭を生やし、洋服姿で眼鏡をかけている。築地小劇場のパーティーに雑誌「演劇新潮」の仲間と共に出席した。この際、酔いに任せて小山内薫の演劇論に割って入り、彼の演出した『休みの日』の翻訳ミスを得意げに指摘。この攻撃によって小山内を閉口させるが、リーダー格の菊池寛に窘(たしな)められ、それ以上の追及は断念している。没後、岸田國士戯曲賞が設立されることになる。実在の人物、岸田國士がモデル。
岡本 かの子 (おかもと かのこ)
夫の岡本一平、息子の岡本太郎と白金三光町で暮らす女流歌人。年齢は1923年(大正12年)の秋の時点で34歳。耳隠し風の髪型で、着物を着ている。17歳にして女流歌人・与謝野晶子に才を見いだされ、文芸誌「明星」で歌壇に進出し、「スバル」や「青踏」誌上でも活躍した。23歳で第一詩集、29歳で第二詩集を出版するなど文才に恵まれた一方で、生活力が低く、書き物を始めると周りが見えなくなってしまう。川口松太郎が現れた際には来訪に気づかなったばかりか、意図せずに渋茶を飲ませてしまい、一平に泣きついている。また仏教に傾倒しており、勉強中は誰の呼び掛けにも応じないが、我に返って溺愛する太郎を見つけると途端に抱きつくなど、情緒不安定な振る舞いが目立つ。しかし、松太郎が小説家を志していることを見抜くなど鋭い観察力を持ち、自分の口紅が移ったたばこを松太郎に勧めるなど、色っぽい所作を見せることも多い。その魅力は一平から「天女」とまで評されている。のちに築地小劇場のパーティーに洋装で出席し、「大地震以来の素敵な夜」と形容した。また、小山内薫と雑誌「演劇新潮」同人の口論に周囲が騒(ざわ)つく中、満面の笑みを浮かべて状況を楽しんでいた。実在の人物、岡本かの子がモデル。
岡本 一平 (おかもと いっぺい)
妻・岡本かの子、息子・岡本太郎と白金三光町で暮らしている作家の男性。年齢は1923年(大正12年)の秋の時点で37歳。垂れ目で、口髭を蓄えている。漫画散文スタイルを得意としており、今は亡き夏目漱石に才能を認められて「朝日新聞」で連載を行い、流行作家の仲間入りを果たした。かの子を「天女」と評しており、川口松太郎から依頼が舞い込んだ際には、彼女のために命懸けで働くと宣言して依頼を快諾した。その後、一晩にして原稿を仕上げ、松太郎に手渡している。なお、松太郎から女中を雇うように提案されているが、女中を雇うと妻が虐(いじ)められて泣いてしまうという理由で却下している。実在の人物、岡本一平がモデル。
岡本 太郎 (おかもと たろう)
岡本一平、岡本かの子の息子。坊主頭の少年で、年齢は1923年(大正12年)の秋の時点で12歳。川口松太郎くらいの若い男性が苦手で、初対面の際には松太郎に素っ気ない態度を取り、一平に叱られている。また、松太郎が勉強中のかの子に声を掛けようとした際には、松太郎の尻に前蹴りを食らわせて阻止し、ガキ呼ばわりされている。しかし、本当の両親を知らないという松太郎の身の上話に感じるところがあり、松太郎が去る際に自作の抽象画をプレゼントした。のちに芸術家として大成することになる。実在の人物、岡本太郎がモデル。
国枝 史郎 (くにえだ しろう)
怪奇小説、幻想小説を得意とする作家の男性。年齢は1924年(大正13年)の冬の時点で37歳。和服姿で色眼鏡をかけており、杖をついている。雑誌「苦楽」誌上で、小田富弥の挿絵付きで『神州纐纈城』を連載することになった。その出来栄えは川口松太郎から世紀末的な怪奇と猟奇的な風情を備えており、新年号にふさわしい傑作であると絶賛された。実在の人物、国枝史郎がモデル。
小田 富弥 (おだ とみや)
「大阪朝報」で連載小説の挿絵を担当していた男性。年齢は1924年(大正13年)の夏の時点で29歳。角刈りで、バンカラ気質。癲狂院(てんきょういん)への強制入院の憂き目に遭っていた岩田専太郎のピンチヒッターとして白羽の矢が立ち、花街で遊女の裸体を絵にしていたところを川口松太郎にスカウトされ、雑誌「苦楽」で筆を執ることになった。その実力は入院中の専太郎に脅威を感じさせたほどで、小田富弥の才能を見いだし、引き抜きを命じた植村宗一は「掘り出しもん」と評価している。国枝史郎の『神州纐纈城』の挿絵を担当した際には、岩田風のペン画というオファーにみごとに応えて作品の雰囲気に合った挿絵を描き上げており、松太郎から称賛されている。のちに、『丹下左膳』や股旅物で時代劇の定番となるビジュアルイメージを作り上げ、「東の岩田専太郎、西の小田富弥」と評される大人気挿絵画家となる。実在の人物、小田富弥がモデル。
中山 豊三 (なかやま とよぞう)
プラトン社の社長を務める男性。下膨れで恰幅のよい体型で、スーツを着用している。小山内薫の紹介であれば問題はないと語り、川口松太郎の入社を即断即決してしまった。著名な作家である芥川龍之介、菊池寛、久米正雄、里見弴に原稿を書かせるという怪しげな証文を携えてプラトン社を訪れた植村宗一に対しては疑いの目を向けていたが、渡りに船と思い直して入社を認め、松太郎と組んで新雑誌を編集するように命令した。実在の人物、中山豊三がモデル。
山名 文夫 (やまな あやお)
プラトン社の男性社員。年齢は1924年(大正13年)の春の時点で27歳。口髭を蓄えており、裾の短い長袍(チャンパオ)風の服を着て、眼鏡をかけている。主に雑誌「女性」の美術面を担当している。岩田専太郎のつてで巷を賑わせていた美少女・岩田とし子を呼び、桜舞うプラトン社で旗袍(チーパオ)姿の彼女を写真に収めた。この際、彼女をミューズと表現し、高名な芸術家の例を列挙したうえで、芸術の湧く泉には必ずミューズが存在するという持論を展開した。のちに堂島ビルディングの屋上で、川口松太郎と専太郎のツーショットを撮影することになる。実在の人物、山名文夫がモデル。
松阪 寅之助 (まつざか とらのすけ)
プラトン社の男性社員。年齢は1923年(大正12年)の秋の時点で51歳。目がぎょろぎょろとしていて、スーツ姿で眼鏡をかけている。元「大阪朝日新聞」の記者で、業界に携わって30年のベテラン編集者として知られている。雑誌「女性」の編集室で働いており、新人の川口松太郎が植村宗一の要望で原稿料の前借りを頼み込んできた際には、毅然とした態度で上方の商売を舐めるなと威圧してみせた。しかし、結果として前借りを許可し、森田に原稿料の支払いを命じている。
森田 (もりた)
プラトン社の女性社員。耳隠しの髪型で、洋服を着ている。主に雑誌「女性」の編集室で働いているが、配属の異なる川口松太郎への電話の取り次ぎ、丁稚(でっち)へのお茶出しなど、雑務全般をこなしている。松太郎が財布を紛失したことに気づかず無銭飲食をしてしまった際には、店まで迎えに行って代金の支払いを済ませたうえで店員に頭を下げるという貧乏くじを引かされる羽目になった。なお、原稿料の前借り常習犯である植村宗一を警戒しており、金遣いの荒い植村に容易に金を渡さないよう、松太郎に釘を刺している。
香西 織江 (こうざい おりえ)
「五郎丸」の芸名で芸者をしている女性。年齢は1923年(大正12年)の秋の時点で22歳。島田髷を結い、華やかな着物を着ている。植村宗一と恋仲にあり、いっしょにプラトン社を訪れたこともある。植村が川口松太郎を伴って茶屋遊びに興じた際には、舞踊「花紅葉士農工商」(文売り)を披露した。なお、植村とは自身が愛人に過ぎないことを理解したうえで関係を続けており、植村が彼より六つ年上の妻、7歳の娘・木の実、3歳の息子・晃生を抱えていることも把握している。
集団・組織
プラトン社 (ぷらとんしゃ)
川口松太郎と植村宗一が働くことになった出版社。クラブ歯磨き、クラブ白粉(おしろい)などの商品を主力とする化粧品会社・中山太陽堂を母体としており、1922年(大正11年)に雑誌「女性」を出版するために創業された。中山太陽堂の社長・中山太一の弟である中山豊三が社長を務めている。共同出資者にして副社長の河中作造は豊三の妻・イトの兄であり、大阪市谷町5丁目20番地にある河中家の屋敷がプラトン社の社屋として利用されている。この社屋は立派な梁のある建物で、ビロード敷の豪奢な内装になっている。しかし、松太郎と植村の職場である第二編集室は社屋ではなく、物置として使用されていた薄暗い蔵の中に設置された。1925年(大正14年)に大阪北区堂島に建てられた堂島ビルディングの四階へと引っ越している。
場所
築地小劇場 (つきじしょうげきじょう)
1924年(大正13年)6月13日に、小山内薫と洋行帰りの演出家・土方与志によって設置された、日本で初めての新劇常設劇場。杮(こけら)落としとして、土方が演出を手掛けた『海戦』が上演された。表現主義の演出は小説家の川端康成、から絶賛され、同じく小説家の横光利一も川端に同意していた。しかし、著名な作家が集結した上演後のパーティーで「今後、2年間は翻訳劇のみ執り行う」とした小山内の発言が問題視され、小山内を中心とする劇場の派閥と、菊池寛を中心とする雑誌「演劇新潮」の派閥のあいだで口論が勃発し、確執が生じる事態となってしまった。なお、『海戦』に感動した岩田とし子は築地小劇場の研究生になることを決意している。
その他キーワード
苦楽 (くらく)
プラトン社が刊行を予定している新しい文芸雑誌。新入りの川口松太郎と植村宗一を中心に編集作業が行われ、1923年(大正12年)12月に創刊号が刊行されることになった。創刊号の執筆陣には里見弴、小山内薫、岡本綺堂、久保田万太郎など錚々(そうそう)たる作家が並び、特別付録として五大作家戯曲集も用意された。のちに岩田専太郎、小田富弥などの挿絵画家も参画し、大衆文芸の草分け的な雑誌へと成長を遂げることになる。なお、当初は「ライフ」という誌名での出版が予定されていたが、小山内の一存で「苦楽」に改題された。
ミューズ
ギリシャ神話に登場する女神の名前。山名文夫によれば、芸術の湧く泉には必ずミューズが存在するという。山名は岩田とし子の美しさをミューズに例えたうえで、エドゥアール・マネにはヴィクトリーヌ・ムーラン、オーギュスト・ロダンにはカミーユ・クローデルが存在したなど、幾つかの事例を挙げて、岩田専太郎のミューズがとし子である可能性を示唆した。
書誌情報
エコール・ド・プラトーン 1巻 リイド社〈[torch comics]〉
第1巻
(2019-02-01発行、978-4845860111)
エコール・ド・プラトーン 2巻 リイド社〈torch comics〉
第2巻
(2020-04-01発行、978-4845860494)