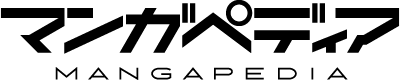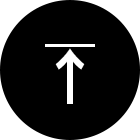概要・あらすじ
登場人物・キャラクター
宮藤 武晴 (くどう たけはる)
日本映画株式会社(日映)所属の大部屋俳優。物語開始時点では入社一週間の新人り。初めての現場で段取りを無視し、スター・市岡歌蔵に斬りかかったことで一時は干されてしまう。その後、殺陣の名手奥村の稽古を受け復帰。殺陣の才能を見せ、「斬られ役」(カラミ)として頭角を現していく。その後、現代劇を増やすという日映の改革により、重要な役を得て、スターの座に躍り出ることとなる。 満州からの引き揚げ組で、幼い頃から満洲映画協会(満映)の撮影現場を遊び場としており、風間俊一郎とはそこで出会っている。左手にある火傷のあとも、そのころついたもの。また、少年時代、満州に出征中だった日映四天王のひとり・伊達源八から、殺陣の稽古を受けている。
風間 俊一郎 (かざま しゅんいちろう)
日本映画株式会社(日映)所属のフォース助監督。物語開始時点では入社一週間の新人り。「リアル」な映画を追い求め、古い慣習を重視する他の関係者たちと対立する。師岡大善監督、高羽実行の助監督を経て、巨匠・森島貢監督の助監督を務めた。その後、埋もれている人間にもチャンスを与えるという日映の改革によって行われた「脚本コンクール」を勝ち抜き、監督の座を得る。 満州からの引き揚げ組で、父は満州のナガトホテルの支配人。宮藤武晴とは満洲映画協会(満映)で出会っており、宮藤とは逆の右手にある火傷のあとも、そのころついたもの。
市岡 歌蔵 (いちおか うたぞう)
日本映画界に君臨するスター。周囲からは「御大」と呼ばれている。段取りを無視した宮藤武晴を一喝したたき伏せた。その後、宮藤と共演し刀を合わせ、その才能を見込み専属の「斬られ役」(カラミ)に指名した。かつては宮藤が目指すようなリアルで迫力ある殺陣を行っていたが、撮影中の事故により危険な殺陣を封印、安全で流麗な殺陣を行うようになる。 ただし、本気の立ち回りは若かりし頃と変わらず速く、並みの「斬られ役」(カラミ)では付いていけないほど。
市岡 光春 (いちおか みつはる)
歌舞伎の名門市岡家の御曹司。日本映画株式会社(日映)に「第5のスター」として招かれた新鋭。瞬く間に御大に次ぐスターとなる。台本をすべて丸暗記する記憶力と、演技中に何があっても動じない集中力の持ち主。普段は世間知らずでつかみどころのない性格で、方向音痴の気がある。
奥村 (おくむら)
日本映画株式会社(日映)の大部屋俳優。殺陣の腕前は高く、関係者からも一目置かれている。宮藤武晴に稽古をつけ、その才能に太鼓判を押した。
生方 朋子 (うぶかた ともこ)
12歳でデビューしてから年間何本もの映画に出演している国民的人気女優。母親はいわゆる「ステージ・ママ」で、従順に従っている。普段の清楚で可憐な姿はあくまで演じている「仮面」のひとつであり、本当の素顔は自分でもわからない、と風間俊一郎に語った。
高羽 実行 (たかば さねゆき)
日本映画株式会社(日映)の新鋭監督。助監督時代から脚本を書いていたため、監督昇格が早かった。市岡光春のデビュー作となる『双月記』の監督となり、風間俊一郎を助監督に加えた。『双月記』で時代劇に新風を吹き込もうと試みる。
師岡 大善 (もろおか だいぜん)
日本映画株式会社(日映)のチーフ助監督。20年あまり助監督を務め、現在40半ば。穴埋めの企画『踊る犬屋敷』で監督昇進するも、三流の企画に落胆していた。しかし、風間俊一郎の映画にかける情熱を見て、三流の映画を二流にすべく奮闘する。
笹木 多可矢 (ささき たかや)
日本映画株式会社(日映)の監督。御大の『流浪剣』シリーズなど、多くの娯楽作を手がけるベテラン。東北訛りが特徴。かつては文芸監督であった。
森島 貢 (もりしま みつぐ)
日本映画株式会社(日映)の監督。国内外合わせ多数の受賞歴を持つ文芸映画の巨匠。通称・「世界のモリシマ」。常にかけたサングラスが特徴。自分の撮りたい映画のためならば、周囲を顧みない傲岸な人物。
上条 尚弓 (かみじょう なおみ)
日本映画株式会社(日映)社長の娘。日映京都撮影所の副所長に就任する。厳しい徒弟制度など、古いしきたりの映画界を一新するため、現代劇の推進、脚本コンクールの開催などさまざまな試みを行う。しかし、若い女性ということもあり、関係者からは反感を買っている。戦時中『風と共に去りぬ』を見て、映画に一生を捧げることを決意した。
書誌情報
デラシネマ 8巻 講談社〈モーニングKC〉
第1巻
(2011-04-01発行、978-4063729955)
第2巻
(2011-07-01発行、978-4063870275)
第3巻
(2011-10-01発行、978-4063870510)
第4巻
(2011-12-01発行、978-4063870688)
第5巻
(2012-03-01発行、978-4063870947)
第6巻
(2012-06-01発行、978-4063871203)
第7巻
(2012-09-01発行、978-4063871432)
第8巻
(2012-12-01発行、978-4063871715)